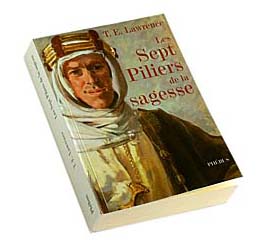 |
|
1,054頁のペーパーバック1巻本で、本体表示の価格25ユーロは平凡社刊の5巻本拙訳の1冊分強にすぎない(エアメール料金を入れて5,153円)。このサイズで1,054頁ということは、口絵、挿画が皆無ということもあって辞書のような紙質の用紙にべた組みで印刷された聖書という感じがする。ただ、紙面は多くのフランス本の例に洩れずきわめて美しい。
また、表紙にオーガスタス・ジョンの描いた有名なアラブ衣装のロレンス像(油彩、テート・ギャラリー蔵)を載せていることが目を惹く。つまり、あとで触れるが2005年に出たAlain Fillion, Lawrence d’Arabie au Moyen-Orient, Édition du Félin, Paris(アラン・フィリオン「中東におけるアラビアのロレンス」)の表紙と同一なのだ。比較的近い間隔で出版された2書の表紙デザインがまったく同じ (画像はこちら) とは、わが国ではちょっと考えにくい。
つぎに、タイトルや扉にはオクスフォード・テキストの翻訳であることの記載がない。裏表紙に記載された内容紹介文を仔細に見るか、拙訳書の「編者序文」にあたる「ジェレミー・ウィルソン序文」を読むまでは既存の仏訳「簡約版」との違いが分からないというわけだ。
肝心の内容だが、訳文を逐一的に検討することは時間的にも能力的にも不可能なので、全体を瞥見したあと、いくつかの点に的を絞って調べてみた。
まず、第一に思ったのは注がないこと――実はそうではなかったのだが、ウィルソン序文の原注16、ロレンスの原注3、訳者(エリック・シェダーユ)による訳注65、計84点の注は、1ヶ所にまとめず当該頁の下に記入する形式のために、当初は大部の本では容易に目につかなかった。注の多寡は訳文の質とは無関係で、余計な訳注などはないほうがいいに決まっている。しかし、『七柱』のような作品を注なしで読むのはむりというものだろう。訳者自身が書かれている内容をよく理解するのに非常な苦労をしたはずなのは、フランスとてわが国と事情はさして変わるまい。他方、近代西欧語による本が欧米で翻訳されるとき、あらためて訳注をつけるのはむしろまれである慣行に照らすと、本書にわずかでも訳注があるのは歓迎すべきことのように思われた。
そこで、私は原注を含む上記の注のすべてを点検してみた。これならごく簡単に、時間をかけずにできるからだ。その結果は別項のとおりで、八木谷さんに見やすい表にしていただいたものである。
これから言えるのは、訳注の項目選定の基準が私にはまったく分からないこと、つぎにかなりな数のどうしようもない過誤があることだ。前者は、誰でも知っているような事項に注をつけながら、調査に努力を要するものを取り上げていないということに尽きる。さりとて、不要な注ばかりかといえば決してそうではない。要するに、注のレベルのバランスがとれず、そして内容に誤りのある割合が多いというわけだ。わずか65点の訳注にキチナーやアレンビーといった人物を入れねばならないなら、想定される読者層は第一次大戦当時の歴史にきわめて疎いということになろう。さような読者がこれほど簡単な訳注で『七柱』を読みこなせるものか、という疑問が生ずる。
つぎに、索引の問題がある。仏訳者が底本としたオクススフォード・テキスト原書が1997年初版限定本なら索引はないが(その場合は一から作らねばならない)、2003年、2004年版には Hazel Bell 作成の索引がついている。単純に翻訳すれば東洋文庫のサイズで縦2列組みにして優に100頁は超える分量の、頁数の列挙ではない、項目を記述内容に応じて小見出しで分割した詳細なものだ。だが仏訳書は「簡約版」の1935年版、ないしはペンギン版で採用された、固有名詞だけの頁数を地名、人名別に羅列するごくありふれた方式を取っている。柏倉俊三訳の簡約版『知恵の七柱』(東洋文庫)もそうだった。
仏訳版の場合、これによると、たとえば「アカバ」は複数頁の連続個所もひとつと数えて約100ヶ所、「ファイサル」は約170ヶ所となって、索引としてはもはや用をなさない。固有名詞以外の事項索引がない点では、英語原書のものと比較にならない。原書索引を翻訳して訳書に利用するのは、今回の拙訳書で八木谷さんが経験したばかりの困難を極める作業である(別ページの「こうして作った 日本語版索引」参照)。対応する頁数が違うのは当然として、原索引作者と考え方が異なるために項目を整理、追加・削減したうえミスを是正せねばならないためだ。それを仏訳者は避けたのか、あるいは原索引は作者(ヘイゼル・ベル)に帰属する独立の著作権の対象なので、何かの理由で利用できなかったのかもしれない。ちなみに、拙訳書の場合は平凡社が原索引の使用権を別契約で買い取ったうえ、日本語版用に改善している。
ともかく仏訳では安易な方法に拠ったわけで、せっかくの訳書の索引としては残念だが評価しかねる。
ついでに、付属地図について一言する。邦訳の巻末折込み地図 (2) (3) に相当するモノクロームものが付されているのみだが、それは制作者こそ異なれ英語原書のものと基本的には同じだ。ただ、地図の記載内容が1935年版あるいはペンギン版のものと、より具体的に言うならば「簡約版」の著作権消滅後に出たペーパーバックのひとつ、1997年刊の Wordsworth Classics 所載のものとあまりにも酷似していることが気になる。むろん、拙訳書第二巻所載の小論でも触れた (p.379) 欠落個所も引き継がれている。
Wordsworth あるいはペンギンブックスとの間になんらかの取り決めがあるならば、第三者が口出しするかぎりではない。だが仏訳本には、著作権でオクスフォード・テキストの1997,2003, 2004年各版の記載はあっても地図に関する説明は見当たらない。
地名(本文内の人名もそうだが)の多くがフランス語式の発音で記入されている(たとえばラム Rum → Roum , ウンム・ラッジュ Um Lejj → Umm Ladjdj, ラービグ Rabigh → Rabir)のは英語版を見慣れた目にはいささか異様だが、固有名詞の表記にお国振りが現れるのは仕方のないことだ。その点でアラビア語原語からの逸脱がもっとも激しいのは日本語のカナ表記である。
本文以外の訳注、索引、地図などから受ける印象は好ましいことではなかったが、問題は訳文そのものがどうかだ。前述したように精査したわけでないので、断定的なことを言う資格はない。だが、だが目を通したかぎりの印象としては正確で丁寧な、そしてきれいなフランス語に訳してあることは分かる。
ロレンスの英語はきわめて癖のある、そして曖昧な表現で充満しているので、仏訳者がそこに気を遣ったとすれば読者には歓迎されるだろう。私は、たまたま自分にとって印象的だった個所の一、二を読み比べてみた。それが私の最大の関心事項だったということではなく、初めのは『七柱』全編を通じてほとんど唯一の滑稽な場面であり、つぎのは訳出で散々手こずった個所のひとつ、という意味である。
[ TOP ]
1. 拙訳書 第1巻 p.338-9‘..and Mirzuk to change the current said, 《He is an unnatural birth, neither raw nor ripe.》’という原文を拙訳では「奴は生まれがまともじゃないのです、未熟でもなければ成熟もしていない」としたのだが、仏訳ではつぎのようになっている。
‘Et Merzouk, pour détourner la conversation: ―Il est né par césarienne, il n’est ni vert ni mûr.’(彼は帝王切開の生まれで、未熟でもなければ成熟もしていない)
unnatural birth には「自然分娩」natural birth に対するものとしてむろん帝王切開も含まれようが、私はよりさまざまな事態、たとえば各種の障害を伴っている場合や何かの理由で周囲の差別を受ける状況などを想定して前記の訳文とした。だが仏訳者は「帝王切開」としている。
フランス語は「明晰さ」が何にも優るとする。有名な文句ではアントワーヌ・リヴァローリ(1753-1801. イタリア系移住貴族)のエピグラム ‘Ce qui n’est pas clair n’est pas français.’(明晰でないものはフランス語ではない)があり、いま言葉も作者も失念したが「あることを言い表すにはただひとつの語しかない」ともいう。
はたしてフランス語がそれほど明晰な言語か、またこの2例が前記格言の対象となりうるかどうかは別として、訳文に感じられるのは叙述を曖昧にしておきたくないらしい仏訳者の態度だといえるだろう。すると、この訳書の文章はオクスフォード・テキストを原文以上に明解な解釈で読み取らせたいという、訳者の意識 的な試みの結果かもしれない。
2. 拙訳書 第5巻 p.154
「近隣のアラブ人がその邪悪な行為の犠牲になって血涙を絞った例は数え切れない。私は、彼らがいつも味わっていた苦しみを思えば相手を殺しはせず、将来、やすやすと暴虐の道具にはならないことをトルコ人に思い知らせるだろう、という気がした」
原文は以下のとおりである。
‘..the Arabs of the neighbourhood had run with tears and blood innumerable times: and I thought that a taste of such bitterness as their customary own would not kill them, but might make them thoughtful for the future, less-docile instruments of tyranny.’
ここでの問題点は、less-docile instruments を将来にアラブが復讐的に用いる暴虐の手段として「死以上に過酷なもの」と取る(アラブにとっては客体)か、アラブ自身をトルコ側が揮う暴虐の相手として 「御しやすくないもの」と取る(アラブが主体)かの2通りの解釈だ。どちらを取るかによって、意味内容は180度ほど変わりうる。当初、私は前者と解し た。すぐ前の p.151 に、ザアルがトルコ人捕虜を「俺たちは、奴らを村びとの息子や娘に下僕として呉れてやった」という、死よりも屈辱的な見せしめの方法が描かれていたから だ。しかし、そのような過酷な (less-docile) 手段で多数の捕虜を処理できるわけでないと思い、より穏当な後者の解釈が適切と考え直した。
そして仏訳を見れば拙訳と同じくこうなっていて、私は納得できた。
‘..et j’estimai que ce retour des choses ne les tuerait pas et leur apprendrait peut-être à ne pas se faire à l'avenir les si docile instruments de la tyrannie.’(「将来、暴虐のあまりにも従順な道具とはならないことを悟らせる」)
わずか2例での即断は避けるべきにせよ、仏訳者はロレンスの曖昧な語法を排し、話の運びがはっきりして誰にも分かるような配慮を払っているように感じられるのだが、それが見当違いでないことを希望したいと思う。
つぎに、英語原書と仏訳版の索引を対照していた八木谷さんから特定の項目、なかんずく原書索引で10ヶ所しかない「ナジュド」(ロレンスの表記では Nejd)という地名が仏訳 (Nedjed) では22ヶ所も挙げられているのはどういうわけか(訳書のほうが多く、しかもその差がありすぎる)というもっともな質問を受けたので、その前後を点検してみた。
「ナジュド」の原意は「高地、高原」で、半島中部の大高原を地域名として指す場合(固有名詞)と、ロレンスがアカバ東方の台地を言う場合(普通名詞)の両用があり、索引には双方が示されている。
Hazel Bell の索引数が少ないことに規則性は見られず、手作業での索引作成における単なる見落とし、ないしはなんらかの意図による割愛にすぎないと分かったが、訳文の実際をチェックする機会ともなった。前記の例文不足を補う意味で、これら 22ヶ所の仏文の実例を引いて参考に供したい。 原文頁数、仏語版頁数、邦語訳文の順に記し、邦訳には掲載の巻数、頁数を示した。英語原書に索引があるものは、1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 13 (3項目), 17, 22 の10点だった。索引に記載のあるものはテーブルに色をつけることで区別した。邦訳のページ数の頭にある数字は巻数を示す。(「1/p.69」=第1巻69ページ)
[ TOP ]
| 1. | 英 | p.14 ― To the west of the oases, between them and the Hejaz hills, it was called Nejd, and... |
| 仏 | p.39 ― À l'ouest, entre lesdites oasis et les hauteurs du Hedjaz, il prend le nom de Nedjed et... | |
| 日 | 1/p.68 ― (オアシス群と)ヒジャーズ山地との間にあたる西のほうでは砂漠はナジュドと呼ばれ、…… | |
| 2. | 英 | p.15 ― which ran down from the complex of hills east and north toward the deserts of Nejd. |
| 仏 | p.41 ― qui rayonnent vers l’est et le nord en direction des déserts du Nedjed. | |
| 日 | 1/p.71 ― そこは東と北のほうで複雑に入りくんでいる山地からナジュドの砂漠に流れ出る、…… | |
| 3. | 英 | p.16 ― which had gone from there and might be found today in Nejd, ... |
| 仏 | p.42 ― et que l'on retrouve aujourd'hui dans le Nedjed, ... | |
| 日 | 1/p.72 ― そこを離れて、現在ではナジュド〔…〕のほうにまで移っている。 | |
| 4. | 英 | p.59 ― cushions of Nejd leather-work.... |
| 仏 | p.93 ― coussins en maroquinerie du Nedjed, | |
| 日 | 1/p.153 ― ナジュドの革を使った〔…〕クッションは、…… | |
| 5. | 英 | p.66 ― pilgrims or merchants ...on their way from Medina to Mecca or from Nejd, ... |
| 仏 | p.101 ― de pèlerins ou de marchands ... allant de Médine ou du Nedjed à La Mecque. | |
| 日 | 1/p.166 ― メディーナかナジュドからメッカへ向かう巡礼や商人…… | |
| 6. | 英 | p.77 ― had spent an exile of two years in Nejd with ibn Rashid ... |
| 仏 | p.114 ― avait passé deux années d'exil dans le Nedjed en tant que secrétaire d'Ibn Rachid. | |
| 日 | p.187 ― ナジュドへ追われて二年間をイブン・ラシードの秘書として過ごした。 | |
| 7. | 英 | p.110 ― Ali the standard bearer, a splendid wild man from Nejd, .... |
| 仏 | p.154 ― Ali, le porte-étendard, splendide et farouche guerrier natif du Nedjed, ... | |
| 日 | 1/p.246 ― 旗手のアリーはナジュド生まれの、野生的なすばらしい男で、…… | |
| 8. | 英 | p.134 ― a present from the Emir of Nejd to his father, ... |
| 仏 | p.182 ― cadeau de l’émir du Nedjed à son père, ... | |
| 日 | 1/p.292 ― それはナジュドのアミールから父に贈られたもので、…… | |
| 9. | 英 | p.143 ― These Ageyl were Nejd townsmen, ... |
| 仏 | p.193 ― Ces Ageyl étaient des citadins du Nedjed, ... | |
| 日 | 1/p.308 ― これらウカイルはナジュド地方の町の出で、…… | |
| 10. | 英 | p.144 ― only it was Nejd they had lost, and the women of the Maabda, ... |
| 仏 | p.195 ― Sinon que c'était le Nedjed qu'ils avaient perdue, ainsi que les femmes des Maabda, ... | |
| 日 | 1/p.311 ― もっとも、彼らの失ったのはナジュド、そしてマアーブダ族の女たちで、…… | |
| 11. | 英 | p.247 ― with household words and phrases from the limpid Nejdi, ... |
| 仏 | p.320 ― vocables familiers empruntés au parler limpide du Nedjed. | |
| 日 | 2/p.178 ― 明快なナジュド弁の日常語や言いまわしと、…… | |
| 12. | 英 | 12. p.267 ― She was the pedigree camel given by ibn Saud of Nejd to King Hussein... |
| 仏 | p.344 ― Il s’agissait de la bête de race offerte par Ibn Saoud, émir du Nedjed au roi Hussein | |
| 日 | 2/p.217 ― ナジュドのイブン・サウードからフサイン王に〔…〕譲られた、血統がしっかりしていて、〔…〕すばらしい牝だった。 | |
| 13. | 英 |
Three items in pp.277-278. p.277 ― to take coffee with them, while listening to their Nejdi Arabic p.277 ― in a set-back which the forces of Nejd had suffered p.278 ― with the dring-drang, dring-drang pestle strokes of village Nejd |
| 仏 |
pp.356-1 ― pour prendre le café avec eux et prêter l’oreille à leur arabe nedjedi. pp.356-2 ― un revers essuyé par les combattants du Nedjed pp.356-3 ― dring-drang, dring-drang -, bruit familier dans les villages du Nedjed | |
| 日 |
2/p.235 ― 一緒にコーヒーを飲み、彼らの話すナジュドなまりのアラビア語に耳を傾けた。 2/p.236 ― ナジュド軍が〔…〕敗北したときに 2/p.236 ― ナジュドの村の流儀で乳棒を使い、〔…〕ごろんごろん、ごろんごろんと擂〈す〉って粉にする。 | |
| 14. | 英 | p.291 ― a drover bringing fifty sheep from Nejd towards his market in Damascus |
| 仏 | p.371 ― conducteur de bétail ... menant cinquante moutons du Nedjed pour les vendre à Damas | |
| 日 | 2/p.260 ― ナジュドから羊五十頭を連れてダマスカスの市場へ向かっていた家畜商人 | |
| 15. | 英 | p. 439 ― over the pink and green valleys of Nejd to Rum. |
| 仏 | p.549 ― vers le Roum en suivant les vallées rose et verte du Nedjed. | |
| 日 | 3/p.214 ― ピンクと緑色をした卓上地〈ナジュド〉の谷を越えてラムへ…… | |
| 16. | 英 | p.472 ― in the quick, broken-kneed Nejd pace …... |
| 仏 | p.589 ― de ce pas rapide et délié qui se pratique dans le Nedjed... | |
| 日 | 3/p.279 ― 前膝を折ったナジュド地方独特の側対速歩の摺り足で…… | |
| 17. | 英 | p. 507 ― in the ascent of Nejd, ….. |
| 仏 | p.631 ― dans l’ascension du Nedjed, ….. | |
| 日 | 3/p.347 ― 台地〈ナジュド〉を登っていると…… | |
| 18. | 英 | p. 521 ― he had taken service with ibn Saud, Emir of Nejd. |
| 仏 | p.649 ― il était allé prendre service auprès d’Ibn Saoud, émir du Nedjed. | |
| 日 | 4/p.39 ― ナジュドのアミール、イブン・サウードに仕えた。 | |
| 19. | 英 | p. 524 ― the nervous limber Nejdi villagers ….. |
| 仏 | p.652 ― ces souples et nerveux villageois du Nedjed ….. | |
| 日 | 4/p.43 ― 苦労性で体の柔軟なナジュドの村びとだ。 | |
| 20. | 英 | p.582 ― useless was their suggestion that he might go away to his home in Nejd. |
| 仏 | p.723 ― il n’écouta le conseil qu’ils lui donnèrent de rentrer chez lui dans le Nedjed. | |
| 日 | 4/p.157 ― ナジュドのふるさとへ帰ることを勧めても同じく無駄だった。 | |
| 21. | 英 | p. 598 ― the tiny hand of these unripe Nejd fellows. |
| 仏 | p.742 ― la main courtaude de ces jeunes types du Nedjed. | |
| 日 | 4/p.188 ― こういったナジュドの未成年によくある、小さな手だった。 | |
| 22. | 英 | p.650 ― under the red cliffs of Nejd ….. |
| 仏 | p.805 ― sous les falaises rousses du Nedjed …. | |
| 日 | 4/p.289 ― 台地〈ナジュド〉の赤い断崖の下を過ぎ、…… |
[ TOP ]
以上の原文はすべてごくありふれたものなので検討の対象としては適当でないが、16. の仏訳には疑問がある。原文の broken-kneed を私は「(駱駝が重心を低くして上下動が小さくなる調教をし)側対速歩の摺り足ができるように膝を折ること」と解したが、仏訳者は単純に「(縛られていた膝が)ほどかれた (délié) 速い歩調で」としている。broken が délié の意になるかどうかは別としても、縛った脚を解くことが乗り手の負担が少ない歩調にはつながらないと思うが、実情を知らないので確たることは言いかねる。いずれにせよ、本書のように長大でしかも厄介な語法が多用された作品の場合は、私の訳者としての自戒と弁明を籠めてのことだが個別的な点検が通用しにくいにちがいない。そのうえで、フランス語版の訳注と索引はあきらかに不適切の批判を免れないだろうし、本文の訳文は訳者の意図がどこにあるかは別として分かりやすい、明快な文章と言えると解する。
最後に、冒頭で触れた別著「中東におけるアラビアのロレンス」について一言しておく。
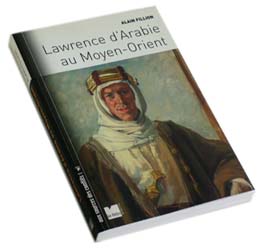 |
あとの点では、フランスで出た多数のロレンス関連本にはロレンスの足跡を辿れるものがないと言う(「既存の『知恵の七柱』や『砂漠の反乱』のフランス語版は正確な地図をまったく載せていず、活動が位置づけられる地点については読者を永遠の疑問のなかに放置している」著者序文)。そこでロレンスの生涯を『七柱』のアラビアを中心に概括し、GSGS (英国国防省地理部)1998年作成の関係地図にロレンスの行動記録を上書きする手法でそれを示す、というものだ。
私は、拙訳書第二巻巻末に収録した「アカバへの道――『七柱』の地図を修正する」を執筆中に同書の存在を知り、ただちに入手して一見したのだが、私の関心があった修正問題とは接点すらなく、結果として役には立たなかった。 ただ、冒頭に述べたように表紙デザインが今回の仏訳オクスフォード・テキストと共通するという点で興味を惹くので、参考までに供覧に付したい。
- * 八木谷注:同じ肖像画を表紙に用いた英語の関連書は、2004年のStephen E. Tabachnick, Lawrence of Arabia: An Encyclopedia、1988年の Malcolm Brown & Julia Cave, A Touch of Genius やNPGカタログなどがある
[ TOP ]
訳注について
序文で16点(編者の原注)、本文で原注3点、訳注65点、計84点の注の内容を以下に示す。これら84点のすべてが、邦訳書では巻末訳注と一部は本文内割注で取り上げられている。ちなみに、邦訳書の場合は編者序言、編者解題の原注104点(およびそれに付した20 点の割注)、本文内のロレンス原注3点、訳注314点、それに本文内にほぼそれに相当する数の割注がある。フランス語訳注はきわめて簡単なもので、解説というよりは「手がかり」に近い。例:アレンビー「英国の将軍 (1861-1936)」
- 訳注の見出しに付した記号はつぎのとおり。
- ×(6件)――誤り。
- △(3件)――記載内容が当を得ず、あるいは部分的に誤りで注として不適なもの。
- ?(1件)――説明の根拠不明で注としての適否を判断できないもの。
- 無印――ほかすべてで、妥当なもの。
- ×△?の各項についてはフランス語の注を翻訳して《 》内に記載し、不適切の理由を付した。
| ジェレミー・ウィルソン序文 | ||
|
16点の原注は英語原文に対応する(仏訳者による訳注はない)。ただし、引用された書名や書簡の略記に留めてあるため、これだけでは出典の詳細を知ることはむずかしい。 例:拙訳 第1巻 p.41 (4) T.E. Lawrence to Robert Graves, 12.11.1922, T.E. Lawrence to his Biographers Robert Graves and Liddell Hart (London, Cassel, 1963), p.23 ⇒ Lettre à Robert Graves (12 novembre 1922).(ロバート・グレイヴズへの書簡 〈1922年11月22日〉) | ||
| 本文 | ||
| 序説 | 梗概 | キチナー △ 《英国の軍人、政治家 (1850-1916)、1911年に駐エジプト総領事、ついで1914年8月に陸相就任》。アラブの反乱開始の日に北海で行方不明(戦死)となったため『七柱』の記述には直接の関わりがないことが読み取れない [ 1/p.48 ] |
| 1章 | アレンビー [ 1/p.55 ] | |
| 2章 | 1. ヤフー [ 1/p.63 ] 2. ムハンマドの棺 × 《棺はメッカのさるモスク内で宙吊りになっているといわれる。合理的に考える人は、ドームが磁鉄鉱でできていて磁力を発するとする》。棺の所在地メディーナをメッカと誤解 [ 1/p.64 ] | |
| 5章 | プラトーンのギリシア語引用 [ 1/p.79 ] | |
| 6章 | ジョン・ウィルクス [ 1/p.90 ] | |
| 8章 | 第二のビルマ [ 1/p.114 ] | |
| 第1部 | 1. マフムト・シェヴケト [ 1/p.147 ] 2. ワクフ相 × 《両聖都担当》。説明が誤っているだけでなく、ワクフの原義と1826年設立のワクフ省に関わることが読み取れない [ 1/p.147 ] 3. エジプト軍シルダール [ 1/p.149 ] 4. 統一進歩団 [ 1/p.149, *16 (p.358) ] | |
| 12章 | 1. イドリースィー [ 1/p.152 ] 2. ガートルード・ベル [ 1/p.154 ] | |
| 16章 | 「サイイドナー」 [ 1/p.198, 「正誤表」 ] | |
|
| アズィーズ・アル‐ミスリーが1911年に経験したこの空爆が史上初の空襲だったこと [ 1/p.213 ] | |
| 第2部 | 19章 | 1. クラウゼヴィッツ [ 1/p.233 ] 2. ジョミニ [ 1/p.233 ] 3. マハン [ 1/p.233 ] 4. フォシュ [ 1/p.233 ] |
| 20章 | 「カイマカーム」 [ 1/p.242 ] | |
| 21章 | 「ミドファ・アッ‐スフール」 [ 1/p.254, 「正誤表」 ] | |
| 25章 | 「赤毛の〈ジンジャー〉」の意味 [ 1/p.297 ] | |
| 26章 | 「ララゲー」 [ 1/p.311 ] | |
| 27章 | ジョン・サックリング [ 1/p.327 ] | |
| 28章 | 1. サアダとアシュラーフ [ 1/p.334 ] 2. カルバラー [ 1/p.334 ] 3. ウェイヴェル △ 《両聖都へ向かうのにヒジャーズ鉄道を利用した最初の白人キリスト教徒》。文意に合う説明をしていない [ 1/p.335 ] | |
| 第3部 | 30章 | 「フィヌム」 [ 2/p.25 ] |
| 31章 | フィッツモーリス [ 2/p.33 ] | |
| 35章 | 1.「イェニ・トゥラン」 [ 2/p.75 ] 2. 原注 [ 2/p.85 ] | |
| 第4部 | 43章 | 1.「アブー・サアド」 [ 2/p.181 ] 2.「ガロン」 [ 2/p.189 ] |
| 46章 | 1. パルグレイヴ [ 2/p.216 ] 2. ブラント [ 2/p.216 ] 3.「ビサートゥ」 × 《ちょっとした広がり》。ここでの意味「カーペット」が示されていない [ 2/p.218 ] | |
| 48章 | シェイクスピア大尉 [ 2/p.235 ] | |
| 49章 | 原注 [ 2/p.253 ] | |
| 50章 | 1.「ナブク」 ? 《ふつうは肥沃な小高地》。邦訳書第2巻 p.264割注で述べた説明とは別に、このような原意の異語があるかどうかは不詳 [ 2/p.264 ] 2.「アブー・カスル」 [ 2/p.264 ] | |
| 57章 | 「究極の未練」(アーネスト・ダウソンの詩) [ 2/p.330 ] | |
| 第5部 | 60章 | 1.「ベリンダ」 [ 3/p.33 ] 2. ガイ・ドーニー [ 3/p.37 ] 3. チェトウッド [ 3/p.37 ] 4. ヴィリーゼン [ 3/p.37 ] |
| 63章 | 1. オッペンハイム [ 3/p.65 ] 2. シャイフ・シャウィーシュ [ 3/p.65 ] | |
| 65章 | F・ベーコンの「王国の真の偉大について」 [ 3/p.76 ] | |
| 66章 | ファルケンハイン [ 3/p.86 ] | |
| 67章 | 1. ダラム [ 3/p.104 ] 2. ノース [ 3/p.104 ] | |
| 第6部 | 77章 | 1.「ジェマダル」 [ 3/p.204 ] 2. ジョージ・ロイド × 《ロイド‐ジョージ (1863-1945) ―英国の政治家。軍需相、ついで陸相。ヴェルサイユ条約の締結交渉で支配的な役割を演じた》。ここで初出のジョージ・ロイド George Lloyd の注に全然別人のロイド‐ジョージ David Lloyd George を取り違えて載せたうえ、その事績では肝心の戦中の首相在任に触れていない [ 3/p.205 ] |
| 80章 | 「ファッラーフ」 [ 3/p.245 ] | |
| 81章 | トム・ティッドラーズ・グラウンド × 《チャールズ・ディケンズの小説。1851年作》。原意の遊びには触れずにここでは無関係な小説名を記入したため、訳注として意味不明。また同著は1861年作なので二重の誤り [ 3/p.258 ] | |
| 82章 | ‘Numen inest.’ [ 3/p.265 ] | |
| 88章 | 1.「タラス」 × 《ここでいうタラス Terras には、ベドウィンにとって同じように侮蔑的な二つの意味がありうる。ひとつは歩兵、徒歩の人々、乗用動物を失った戦士などの意、ほかは荷車引きや駄獣追いの人々の意である》。この説明の根拠は不明だが、訳注としては誤り [ 3/p.341 ] 2. テレシウス [ 3/p.345 ] | |
| 第8部 | 「Q」 [ 4/p.221 ] | |
| 第9部 | 112章 | 1. C.M.G.(聖ミカエル‐聖ジョージ勲位) [ 4/p.284 ] 2. D.S.O.(殊勲賞) [ 4/p.285 ] |
| 114章 | マロリー [ 4/p.308 ] | |
| 115章 | 1. ムタワッキル △ 《ムタワッキルはマムルーク朝最後のスルターン。オスマン朝のスルターン・セリムに敗れ、処刑された(1517年)》。ムタワッキル(三世)はエジプトに残存したアッバース朝カリフの末裔。マムルーク朝最後のスルターン、トゥーマン・バイと混同した点で誤り [ 4/p.323, 「正誤表」 ] 2. メフメト五世 [ 4/p.323 ] 3. ゴタムの知恵者 [ 4/p.325 ] | |
| 125章 | サー・フランシス・ドレイク [ 5/p.54 ] | |
| 130章 | ベンサム主義者 [ 5/p.107 ] | |
| 原注 [ 5/p.211 ] | ||
23/7/2009 たすみ・つねお [ プロフィール ]
| TOP | ■HOME PAGE |